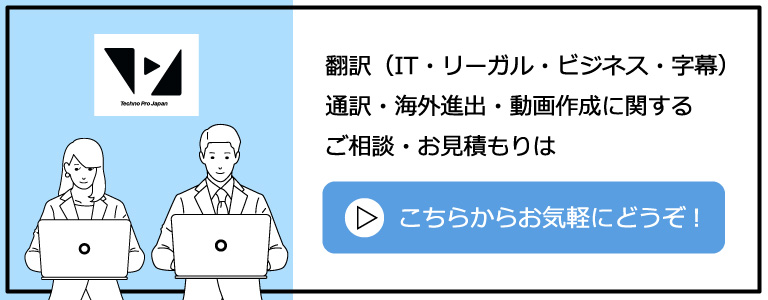この「翻訳者が見た世界の半導体技術」シリーズでは、弊社の半導体翻訳担当スタッフが読んだ世界各地の半導体技術に関するニュースや記事、論文を短く要約してお届けします。翻訳するうえで欠かせない専門知識の拡充や調べ物、最新トレンドのキャッチアップなどを目的に、主に海外の英語情報を収集したものですが、半導体ビジネスにかかわるあらゆる皆さまに役立つものになれば幸いです。
目次
Toggle光子の運動量を変えることで光・物質相互作用の概念をくつがえしたというニュース
Tech Exploristより「Light momentum turns indirect silicon into direct semiconductor」。ざっくり言うと、光子の運動量を変えることで光・物質相互作用の概念をくつがえした、というお話です。
以下、簡単にまとめました。
-
-
- 光を数nm(論文では3nm)以下のスペースに閉じ込めると、運動量が自由光子の千倍(=物質内での電子の運動量並み)にも増える
- ところで太陽電池は、光を半導体などに当てると、電子が光を吸収する現象を利用している(電子遷移)
- 太陽電池で使われるシリコンは「間接遷移型半導体」と呼ばれ、光を吸収して発電する際に運動量の加増が必要で、あまり発電効率はよろしくない=実用的なシリコン太陽電池を作るには単結晶シリコンでも200μm程度の厚さが必要
- 運動量が増えた光子をシリコン(間接遷移半導体)に当てると、従来よりもシリコンの光吸収効率を数桁向上させられる
- この光閉じ込めの機構を組み込めば、シリコン太陽電池の大幅な薄型化=材料削減が可能と期待される※太陽電池には、シリコンとは異なる直接遷移型の材料で作られたものもあるが、耐久性等に難あり
-
太陽電池(光吸収)やLED(発光)の仕組みのわかりやすい解説はこちら:
半導体を使わない能動素子を3Dプリントで製造できるようになる可能性も
MIT Newsより、半導体を使わない能動素子を3Dプリントで製造できるようになるかも…というお話です。半導体不足の昨今では、こういう基礎研究も重視されそうですがはたして…。
※能動素子=ざっくり言えば電気エネルギーを増幅/整流できる部品。半導体を使うのが一般的。
以下、簡単にまとめました。
-
-
- 半導体は能動素子に不可欠な存在だが、生産が簡単ではないので供給量やコストに問題あり
- ポリマーフィラメントに「銅のナノ粒子」を混ぜたものを3Dプリントしたところ、能動素子としてリセッタブルヒューズのような性質を観測できた
- このフィラメントでトランジスタを実装することにも成功した
- 他の材料も模索中だが、現状、銅入りフィラメントでしかこの性質は再現できていない
- フィラメントは半導体と異なり安価で、生分解性もあるので環境にもやさしい
- なお、このフィラメントは3Dプリントで電磁コイルをつくろうとしていたらなぜかできた、とのこと
-
※リセッタブルヒューズ=従来の「溶けて切れる」ヒューズと異なり、繰り返し使えるヒューズ。急激な電圧(温度)の変化が起きると、構造が一時的に変化して抵抗が急激に増大する(=電流を通さなくなる)が、温度が下がるとまた抵抗が小さくなる。