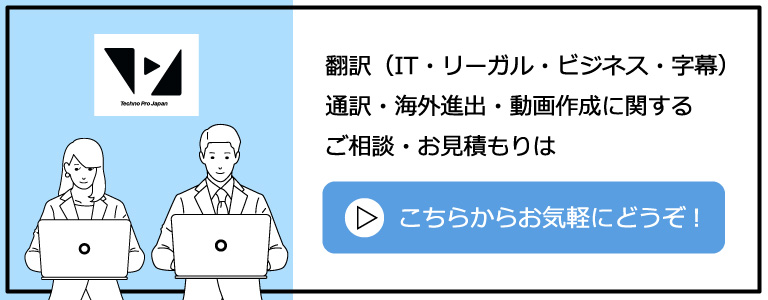この「翻訳者が見た世界の半導体技術」シリーズでは、弊社の半導体翻訳担当スタッフが読んだ世界各地の半導体技術に関するニュースや記事、論文を短く要約してお届けします。翻訳するうえで欠かせない専門知識の拡充や調べ物、最新トレンドのキャッチアップなどを目的に、主に海外の英語情報を収集したものですが、半導体ビジネスにかかわるあらゆる皆さまに役立つものになれば幸いです。
目次
Toggleスタートアップ企業Destination 2D、半導体チップ上にグラフェンを直接形成することに成功
IEEE Spectrumさんより、スタートアップ企業のDestination 2Dが半導体チップ上にグラフェンを直接形成することに成功した、というお話です。
以下、簡単にまとめました。
-
-
- 従来の銅製インターコネクトは線幅を小さくし過ぎると抵抗率が劇的に増加することから、半導体チップの微細化を進めるうえでは材料の変更が必要
- 代替材料としてグラフェンが有力視されているが、「グラフェンの形成には従来のCMOS製造手法では対応不能な高温(摂氏約400度)が必要」かつ「ドーピングなしのグラフェンの電荷キャリア密度は低い」という問題がある
- Destination 2Dの発表によれば、「加圧式の固相拡散法により、グラフェンのインターコネクトを摂氏300度(現状のCMOS製造で実現可能な温度)で直接形成」し、「インターカレーションにより銅の100倍の電流密度も実現」したとのこと
- 銅とは真逆に「配線を細くするほど電流密度を高められる」ので、今後の半導体製造に貢献しそう
-
※そう言えば2024年には、グラフェン製チップが初めて作られたニュースもありました。
余談:上記記事の引用で、マンチェスター大学のグラフェン特集ページにも出会いました。
グラフェン発見の逸話(スコッチテープ法)やその製造法、特性がわかりやすくまとめられています。
原子炉のコア付近に3日間連続で置いても壊れない半導体を発見
米国エネルギー省原子力エネルギー部より、原子炉のコア付近に3日間連続で置いても壊れない半導体を発見したという記事です。
-
-
- 原子炉にはさまざまなセンサー類が必須だが、高温と放射線から精密機器を守るために設置場所をコアから離す必要があり、ノイズ混入や信号劣化の問題がある
- オークリッジ国立研究所のチームが、シリコンよりも熱と放射線に強い窒化ガリウムを使った半導体を原子炉コア付近に3日間置いて実験した
- 窒化ガリウム半導体は摂氏125度という高温の中、標準的なシリコン半導体の100倍にあたる積算線量にも耐えた
- 窒化ガリウムは原子炉内の環境に5年は耐えられるという研究もあり、壊れず精度の高い原子炉用センサーの材料として窒化ガリウムが有望
-
青色LEDやパワー半導体などへの応用をはじめ、次世代の半導体材料として注目されている窒化ガリウム。見る人が見ればこういう使い道も生まれるのですね…!